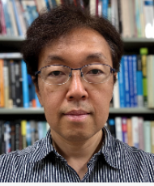Special
2025.11.17 UP
【INTER BEE MEDIA Biz】基調講演「メディアの<信頼>を考える」事前レポート

メディアの<信頼>がいま、問われている。インターネットからの多様な情報の出現により、従来のマスメディアへの無条件の信頼は揺らいでいる。私たちはいま、メディアにとっての<信頼>とは何か、真摯に向き合う必要があるのではないか。INTER BEE MEDIA Bizでは「メディアの<信頼>を考える」と題して基調講演を行い、この難しいテーマに挑む。登壇するのは、東京大学教授の林香里氏、慶應義塾大学教授の津田正太郎氏、そして博報堂メディア環境研究所の山本泰士氏。モデレーターはこのセッションを企画した日本テレビ報道局の三日月儀雄氏が務める。学識者と実務家が一堂に会し、構造変化の読み解きから具体的な回復策まで、メディアの信頼について多角的な議論が展開される。