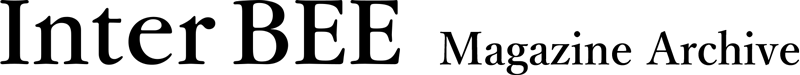【NEWS】3D University JAPAN 2015 報告(3)米Jaunt社のグラント・アンダーソン氏が講演「VR映像文法の確立を急げ」
2016.2.26 UP


パネルディスカッション「HDRの普及へ向けた最新動向」

パネルディスカッション「日本におけるVRの多様なアプローチ」

Jaunt社のグラント・アンダーソン氏

Jaunt ONE
昨年12月に開催した「3Dユニバーシティ・ジャパン(3DU-J)」は、3D映像に加え、4K、8Kに代表されるUHD、HDR(High Dynamic Rate)、HFR(High Flame Rate)、VR、裸眼立体ディスプレー、立体音響、レーザープロジェクション、巨大スクリーンなど、幅広い先進映像を対象にしている。これまで2回にわたり紹介した基調講演、表彰式のほか、「VRとHDRの最前線」と題した講演会が開催され、国内外の最新技術やビジネス動向を解説した。4K HDRやVRのコンテンツ制作に携わる関係者による講演や、研究者などによるパネルのほか、米国のVR開発会社Jaunt社のグラント・アンダーソン氏による特別講演が開催された。
(大口孝之)
■規格が複雑化する4K/HDR
12月11日の最初のプログラムとして、長年にわたって光ディスクの規格化に携わってきたパナソニックの小塚雅之氏による「HDRの基礎と展望」と題した特別講演で幕が開いた。
現在4K/HDRの世界は、メディアごとに様々な規格が複雑に関係している。4Kテレビ放送では、解像度が倍に増やされただけでなく、色空間がHDのITU-R勧告BT.709からBT.2020に拡張された。これはデジタルシネマ業界の規格DCI-P3よりも広い色空間を表現できることを意味する。
もう1つは輝度範囲。人間の眼は瞳孔を調整することで、10000対1という非常に広い輝度範囲をカバーできる。SDR(Standard Dynamic Range)のデジタルカメラでは1000対1が限界で、実際に見た世界とは異なるものになっていた。しかしカメラ側の性能が良くなり、現在の業務用機では16000対1という、人間の視覚特性を超える性能を持つようになってきている。
■人間の視覚特性を超える輝度範囲を実現したHDR
だがBT.709の定める伝送路は1000対1のままで、ここがボトルネックとなっていた。そこでHDR撮影した16ビット浮動小数点データをOETF(Optical-Electro Transfer Function、ガンマ関数、あるいは光電気伝達関数)で量子化することで10ビットの整数データに圧縮し、表示時はEOTF(Electro - Optical Transfer Function、OETFの逆関数、電気光伝達関数)による逆量子化でリニアに戻すという方法で解決された。
このOETF/EOTFの手法にも2種類あり、ハリウッドが提案したSMPTE ST.2084と、NHKやBBCが提案した放送用のHLG(Hybrid Log-gamma)がある。
■トーンマッピングを用いるST.2084、パッケージ用規格とIP配信規格、上映用規格が併存
ST.2084は、ピークをSDRの100nitsから10000nitsに引き上げた絶対輝度で扱う(nitは輝度を示す単位。1nitは1平方mの面積をムラなく1カンデラの明るさで光る輝度)。しかし現実に10000nitsを表示できるディスプレーは製品化されていない。そのため、これをそのまま入力してしまうと、信号が1000nitsあたりでクリップされてしまう。そのため、これを不自然でないように落とし込むため、トーンマッピングという技術が必要になる。
ST.2084は、パッケージ(Ultra HD Blu-ray Disc)用の規格であるHDR10と、IP配信(Netflix、Amazonインスタントビデオ、VUDU、Xbox Videoなど)やドルビーシネマ方式の映画館に採用されているドルビービジョン(日本では未対応)などがある。HDR10は基本的にSDRとの互換性はなく、別個のグレーディングを必要とする。一方ドルビービジョンは、HDRからSDRをリマスタリングして、その差分を別データとして扱うことで互換性を持たしている。
■SDRと互換性を持つHLG方式 ARIBも採用
HLGはピークを1200−2000nitsまでという現実的な数値に最適化して、ディスプレーの性能に合わせて相対輝度で表示する。そのためトーンマッピング処理は不要で、SDRとも互換性がある。こういったことから電波産業会は、4K/8K放送用HDR標準規格としてHLG方式によるARIB STD-B67を策定した。しかしハリウッドはSDRテレビにおける視聴に関して、懐疑的な態度を取っているそうだ。
■パネルディスカッションでソニーPCL、IMAGICAが事例を紹介
小塚氏の講演に続いて、IMAGICAの灰原光晴氏をモデレータとしたパネルディスカッションが行われた。パネラーは小塚氏のほか、パナソニック映像の阿部隆行氏や、ソニーPCLの諏佐佳紀氏、IMAGICAの石井亜土氏が参加した。
阿部氏は『クロアチアの世界遺産 -原始の森と流れる水に響く歌声-』における4K撮影からポスト・プロダクションにおける流れや、UHD BDソフトの『るろうに剣心』の4Kオーサリングなどを説明。『GUNKANJIMA -Traveler in Time-』を手掛けた諏佐氏は、ソニーPCLにおける4K/HDR映像制作フローを解説した。石井氏はIMAGICAにおける業務用ハードウェア製品化の歴史と、HDR評価画像「LUCORE」の開発で必要となった、実際に10000nits表示可能なリアプロジェクターの自社開発などについて述べた。
■「日本におけるVRの多彩なアプローチ」
2つめは、早稲田大学教授でAIS-J会長でもある河合隆史氏をモデレータとした講演とパネルディスカッションだ。まず、河合研におけるVRの生体影響や視機能への影響の研究が紹介され、次いで3タイプのVRについて関係者が登壇して説明した。
最初はシアター型VRの代表として、凸版印刷の佐伯敬太氏が登壇し、これまでの博物館や展覧会における活用例のほか、プラネタリウムや屋外イベント、12Kという超高解像度VRの試みなどについて述べた。
続いてネットワーク型VRについて、ドワンゴの岩城進之介氏が説明。東京・六本木のイベント会場ニコファーレを用いて、ステージ上の透明スクリーンにバーチャルキャラクターが登場するイベントでは、ネット視聴者もVRで同一体験ができる。また360度カメラによるライブ中継をHMDで視聴するという試みについて解説した。
モバイル型VRでは、フジテレビの大村卓氏が『タイムトリップビュープロジェクト』の概要を説明。歴史調査から実写撮影、CG制作などの詳細なメイキングや、スマートグラスを用いて実際の日本橋や江戸城をツアーする様子を紹介した。
■「新たな映像言語としてのVR」
最後に特別講演として、来日した米Jaunt社のグラント・アンダーソン氏が登壇した。13年にシリコンバレーのパロアルトで創業したJaunt社は、シネマティックVRのハードウェア、ソフトウェア、ツール開発をしている。アンダーソン氏は、ソニー・ピクチャーズ・イメージワークスでテクニカルディレクターやステレオスコピック・スーパーバイザーを務めてきた人物で、現在はロサンゼルスに作られたスタジオにおいて、Jaunt社のシステム向けのストーリーテリングやコンテンツ制作に取り組んでいる。
シネマティックVRとは、360度3Dカメラによる実写ベースのVRコンテンツのこと。従来のゲーム主体のフルCGコンテンツとは異なる。彼らはまず、カメラリグ作りから始めたという。最初は、マシンビジョンカメラ24台を組み合わせ、機雷のようにレンズが突き出した球状システムを作成。次に16台のGoProを用いて、頭頂部よりも水平方向の解像度を上げた第二世代を開発した。だが各カメラの完全同期が難しく、専用カメラの必要性が課題となった。
■3Dカメラ24台で4K60pHDR撮影
Jaunt ONEと名付けられた最新モデルでは、元アップル社のコージ・ガーディナー氏が中心となり、Lunar社と提携して独自設計のカメラシステムを採用している。グローバルシャッター方式、4K、60フレーム、HDR、3Dの24台のカスタム・センサー・モジュールを搭載し、マスタースレーブ式で同期させる仕組みだ。またこれらの映像をきれいに繋ぎ合わせる、ステッチングのソフトウェアも開発した。
コンテンツの応用例としては、冒険の記録、ニュース、ドキュメンタリー、スポーツ、コンサート映像、子供向け作品、トラベローグ、短編映画などが構想されている。実例として、ヨセミテ国立公園やユタ州モアブの渓谷で撮影した作品『North Face: The Climb』のメイキングが紹介された。(タイトル上の画像=『North Face:The Climb』のメイキング)
■事例から今後の課題を紹介 「早期にVRの映像文法確立が必要」
しかし実際に撮ってみると、様々な問題が発生する。まず「垂直に切り立つ岩場に、どうやってカメラをどうやって固定するか」である。360度カメラではカメラマンの姿も写ってしまうし、三脚や固定器具も視野に入る。ドローンも用いているが、真上方向も撮っているため、ドローン本体も写り込んでしまう。またカメラ自体の影も問題となる。これらは撮影時にはどうにもならないため、後処理で消去する必要があるのだ。またライブプレビューはできないし、照明もライトが写るため不可能である。また実際にHMDで鑑賞してみると、自分の頭の動きとカメラモーションが鑑賞して気分が悪くなる。そのため、カメラは原則として固定でないといけない。音も問題で、やはり鑑賞者の頭の動きにサウンドの方向が一致しないといけない。これをどうするかは今後の課題となる。
16年は各社からHMDが市販される予定であり、この分野の本格的な立ち上がりが期待されている。それを、90年代のような短期の流行に終わらせないためにも、「早急にシネマティックVR独自の映像文法を確立させる必要がある」とアンダーソン氏は述べた。
(3D University JAPAN 2015 報告シリーズは今回で終了です)

パネルディスカッション「HDRの普及へ向けた最新動向」

パネルディスカッション「日本におけるVRの多様なアプローチ」

Jaunt社のグラント・アンダーソン氏

Jaunt ONE