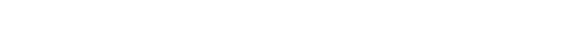Special
2025.05.13 UP
塚本幹夫氏のNAB Show 2025レポート「脱放送か、迷走か。 NAB=全米放送協会が主催する“非放送化”」

今年も4月5日から9日まで米国ラスベガスで開催された全米放送協会によるNAB Show。その現地取材レポートがInter BEEの主催で開催され、映像新聞論説委員の杉沼宏司氏と、株式会社ワイズメディアのメディアストラテジスト塚本幹夫氏がオンラインで講演した。ここでは塚本氏の講演を記事にして紹介する。放送局での幅広い経験を持つ塚本氏の目を通して、2025年米国放送業界の最新動向が伝わるホットなレポートだった。
今年のNAB Showの出展者数は1,100社。来場者の53%が初来場者というのが今年の特徴で、従来の放送関係者が減少し他ジャンルからの参加者が増加している傾向が見られたという。
(メディアコンサルタント・境 治)